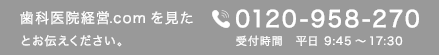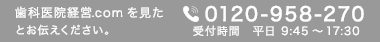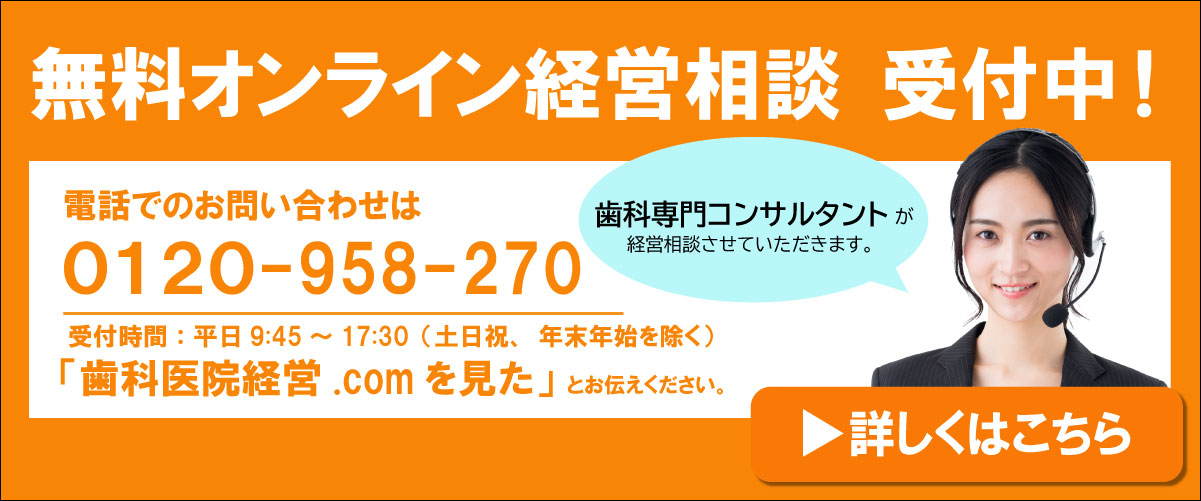ホント?【歯科診療報酬改定速報vol.7_地域格差】中医協資料から読み解く「県別点数」
- コラムテーマ:
- 未分類
いつもお世話になっております。
株式会社船井総合研究所、歯科支援部リーダーの
山本 喜久でございます。
お忙しいところ、こちらのコラムをご開封いただき、誠にありがとうございます。
表題の件、「地域別点数格差」――この耳慣れない言葉が、今、歯科医療の常識を根底からひっくり返そうとしています。中医協から緊急で、極めて重要な資料がアップされたため、皆様にお伝えします。
■中央社会保険医療協議会(中医協)令和7年9月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001560014.pdf
この資料は、2026年歯科診療報酬改定の「進むべき道を示す羅針盤」です。この指針をいち早く掴み、対応を検討することこそ、時代の流れ(時流)に沿った、盤石な歯科診療経営を叶える最速のルートになります。
「時流適応」は社会課題解決のチャンス
「なぜ、そこまで時流にこだわる必要があるのか?」
それはシンプルです。国民皆保険制度下では、国が「進めたい方向」に点数が付く、という構造は絶対だからです。
例えば、根管治療の点数が20年近く変わらない一方で、在宅医療を広める目的で導入されたSPTⅡには、当時840点という破格の高評価がつきました。また前回改定では、「訪問診療にならない人を増やす」という国の強い意志のもと、高齢者の口腔機能管理や、小児の口腔機能発達不全症といった予防・管理系に重点が移りました。
国が推進する方向を知ることは、結局のところ、先生方の医院が「日本の社会課題の解決」に直結し、その貢献に対して点数、つまり収益という形で正当に評価される、ということです。will(やりたい)・can(得意な)・must(求められる)の3軸を見直す、まさに千載一遇のチャンスだと捉えてください。
今回の論点:「地域特性を踏まえた医療提供体制」の衝撃
今回の中医協資料が示す最重要メッセージは、「地域の特性を踏まえ、その地域に必要な歯科医療を提供する仕組みの構築が必要」ということです。
これは、歯科医師の偏在や高齢化による廃院が増え、地域によっては「歯科医療資源の確保」が深刻な課題になっていることへの国の危機感の表れです
。この課題を解決するために、診療報酬というメスを入れることが明確に読み取れます。
つまり、「骨太の方針」と並んで、この「地域ごとの医療格差是正」が、2026年改定の最大の焦点となります。
最重要論点:1点=10円の原則が崩れる可能性
特に、歯科医師の不足する地域の対応については、先生方の経営の根幹を揺るがす、最もセンシティブな論点です。
資料では、都内とへき地との歯科医師数のギャップが鮮明に示され、この解決策として議論されているのが「地域別の保険点数のあり方」です。
これは、私たちが長年当然としてきた「1点=10円」という絶対的なルールが、ついに崩壊するかもしれない、ということを意味します。
・都心部(歯科医師集中地域): 1点が7点や8点に引き下げられる可能性。
・郊外・地方(歯科医師不足地域): 1点が10円以上になる可能性。
国は点数というインセンティブを用いて、医療資源を「足りていない地域」へ強力に促そうとしています。大型医療法人様にとっては、社会貢献と経営を両立させる郊外への新規開業が、一気に現実味を帯びる、極めて重要な検討課題です。
地域別点数格差がもたらす経営戦略への影響
もし、都心で点数が下がり、地方で点数が上がるという格差が導入された場合、各地域で生き残るための経営の重点は、極めて明確に二分されます。
①郊外・地方(点数UP)の戦略:メンテナンスと管理の徹底
保険診療の収益性が向上する地方では、点数の増加を「一過性のボーナス」で終わらせてはいけません。急性期治療で終わらず、患者さんを地域に定着させることが最大のミッションとなります。
・メンテナンス体制の確立と強化:
高評価となった口腔管理(口管強など)やSPTを積極的に推進し、患者様のリコール定着率を最大化することが、安定経営の生命線です。歯科衛生士(DH)の採用・教育、リコールシステムの自動化への投資は、もはや待ったなしの状況です。
・地域包括ケアへの参画: 医科や介護施設との連携を徹底し、診療圏内における「地域医療の中核」としての地位を確立することで、紹介獲得の盤石な基盤を築きます。
・「量より質」への転換: 保険点数の恩恵を最大限に受けるため、患者様一人当たりの診療時間や回転率ではなく、メンテナンス患者の定着率を最重要指標とする経営へ、考え方そのものを転換しなければなりません。
②都心部(点数DOWN)の戦略:自費率向上と高度専門化
都心部で保険診療の収益性が低下する場合、生き残りの焦点は「いかに自費診療の比率を高め、収益性を確保するか」という一点に集約されます。
・自費診療特化・専門性の追求:
一般診療から脱却し、インプラント、矯正(マウスピース矯正含む)、審美といった専門性の高い自費領域を徹底的に強化します。高度な技術を持つドクター、専門資格を持つスタッフへの投資は、競争優位性を保つための必須条件です。
・カウンセリング体制の圧倒的強化:自費診療の成約率を向上させるため、患者様の価値観や予算を深く理解するコンサルテーションの質を極限まで高めます。これは、保険診療との明確な差を伝えるための、最もプロフェッショナルなプロセスです。
・高付加価値化による差別化:
最新鋭の設備(マイクロスコープ、口腔内スキャナーなど)、徹底したホスピタリティ、快適な空間提供により、患者様が「点数の安い保険診療ではなく、高い費用を払ってでもこの医院で治療を受けたい」と思える“唯一無二の価値”を創出します。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
まずは取り急ぎ、2026年度の歯科診療報酬改定における、この最も大きな方向性のご案内までとなります。
この大きな変化を、私たちは「ピンチ」ではなく「大チャンス」と捉え、時代の波を乗りこなしていきましょう。先生方と共に、日本の歯科医療がもっと強く、もっと患者さんに求められる存在になるよう、私も全力を尽くします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
◾️この記事を書いたコンサルタント

山本 喜久
関西学院大学法学部出身。新卒で船井総合研究所に入社。
大学時代から、難関校専門の塾講師として活躍。その時の経験から「人に教える」ことを最も得意とし、それを応用したカウンセリング体制の構築には定評がある。経営者に寄り添いながら、粘り強く「歯科医院経営者の夢を叶える」ことをコンサルタントとしての信条としている。
LINEはじめました!
LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!
無料経営相談受付中!
メールマガジンのご案内
歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~
歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。