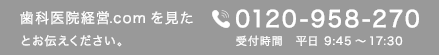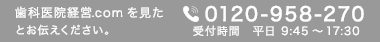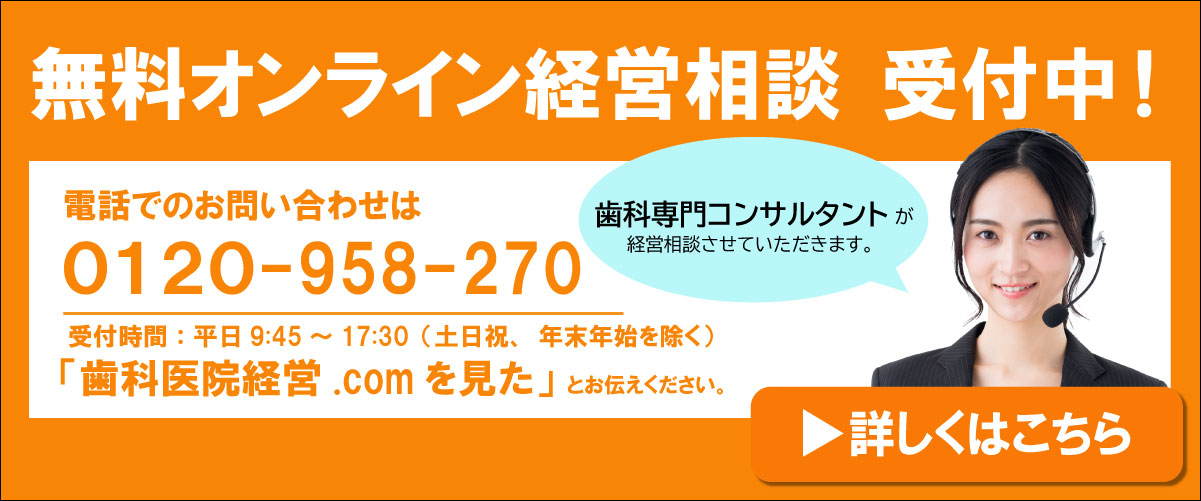【知ってるだけではNG】2026年改定で変わる歯科の常識「食べる・話す」を支える医院とは
- コラムテーマ:
- 未分類
皆様
いつも大変お世話になっております。
株式会社船井総合研究所 歯科支援部リーダーの山本喜久でございます。
本日は、お忙しいところ本コラムをご覧いただき誠にありがとうございます。
さて先日、中医協より「2026年度診療報酬改定」に関する最新資料が公開されました。
医院経営に大きく影響を及ぼす内容が含まれているため、速報としてまとめてご案内させていただきます。
■中央社会保険医療協議会(中医協)令和7年9月10日開催資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001560014.pdf
なぜ「時流に沿った歯科診療」が必要なのか
国民皆保険制度の中では、国が「推進したい方向性」に報酬(点数)が付与される仕組みが明確に存在します。例えば、かつて訪問歯科の普及を目的に創設された「か強診」は、その後「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと進化し、高齢者の口腔機能低下症や小児の口腔機能発達不全症まで対象が広がりました。
これは、国の強い意志――すなわち「訪問診療を支えるだけでなく、その前段階で“食べる・話す”を支援し、訪問診療を必要としない人を増やす」――を如実に表しています。
ですので、「点数が高いから導入する」という表面的な理由ではなく、国がどの社会課題を解決しようとしているのかを正しく理解することが重要です。結果として点数はついてくる。この順序を忘れずに医院経営に落とし込む必要があります。
医院経営における3つの軸
診療方針を考える際に欠かせないのが以下の3つの軸です。
will(やりたい診療)
can(得意な診療)
must(求められる診療)
この3つのバランスを整えることが医院経営の根幹であり、さらに「時流」を把握することで、この軸をより磨き直すことができます。結果として医院が国の方針に沿った形に進化し、社会課題の解決に直接つながる診療を提供できるようになるのです。
今回の中医協資料から読み取れる方向性
今回の資料で明確に打ち出されたのは、「地域特性を踏まえた歯科医療提供体制の構築」です。つまり「その地域に必要とされる歯科医療をどう提供するか」が、かかりつけ歯科医に強く求められる時代が本格的に到来したと言えます。
併せて「骨太の方針」として以下の3つが重視されています。
①糖尿病と歯周病の関わり
②オーラルフレイル対策(口腔機能管理)
③歯科医師不足地域への対応
中でも②「オーラルフレイル対策」は、特に重点的に推進されていくことが予想されます。
口腔機能管理の今後
これまでの口腔機能管理は「低下の有無を確認し、必要に応じて義歯や訓練を行う」ものでしたが、今後は 「治療の結果として生活機能がどれだけ回復したか」 というアウトカム評価へと移行していきます。
具体的な展開のイメージ
評価指標の拡充:咀嚼能力検査や構音評価に加え、栄養状態の測定まで取り入れ、噛める・話せる・栄養を摂れるという総合評価が進む。
診療報酬の変化:単に義歯を装着したかではなく、「介入前後で機能がどれほど改善したか」が報酬の対象になる可能性が高い。
管理栄養士の役割拡大:食べられる食品リストの変化を栄養指導につなげるなど、栄養士が歯科チームの中心的役割を果たす場面が増える。
デジタル技術の導入:咀嚼運動や筋活動を簡易に計測できる機器やアプリの普及、電子カルテでの経時的データ管理、AIによるリスク予測の活用。
医院ブランディングへの波及:「義歯装着から半年後にどの程度咀嚼機能が戻ったか」を数値で示せる医院は、地域や施設からの信頼度が格段に高まる。
すなわち「治療したかどうか」から「治療によって生活の質がどう改善したか」へ――。
この流れに対応できる医院こそ、改定後の時代に患者様や地域から選ばれる存在となるはずです。
その他の注目点
・糖尿病と歯周病:HbA1c測定器の導入などを通じ、歯科側から疾患の早期発見に関わる取り組みが後押しされる可能性があります。
・地域格差の是正:都市部とへき地の診療格差を解消するために、地域別の点数見直しが検討されており、新たな挑戦をする法人の登場が期待されます。
《まとめ》
今回の中医協資料は、2026年度診療報酬改定の方向性を示す非常に重要なものです。
特に口腔機能管理は「栄養指導」「アウトカム評価」「多職種連携」を含んだ包括的な体制への進化が強く求められています。
私どもも今後、さらに具体的な「口腔機能低下症対策フロー」や「管理栄養士の活用策」を整理し、順次ご案内してまいります。
今回の内容を一つのきっかけに、ぜひ医院の診療方針や体制を見直し、未来に備えていただければ幸いです。
そしてこのメルマガでは、今後も「業界の最前線」「医院経営のヒント」「すぐ実践できる取り組み」を分かりやすくお届けしてまいります。
ぜひ次回以降も楽しみにお待ちいただければと思います。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
◾️この記事を書いたコンサルタント

山本 喜久
関西学院大学法学部出身。新卒で船井総合研究所に入社。
大学時代から、難関校専門の塾講師として活躍。その時の経験から「人に教える」ことを最も得意とし、それを応用したカウンセリング体制の構築には定評がある。経営者に寄り添いながら、粘り強く「歯科医院経営者の夢を叶える」ことをコンサルタントとしての信条としている。
LINEはじめました!
LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!
無料経営相談受付中!
メールマガジンのご案内
歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~
歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。