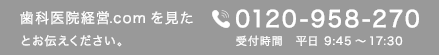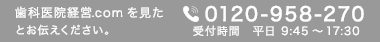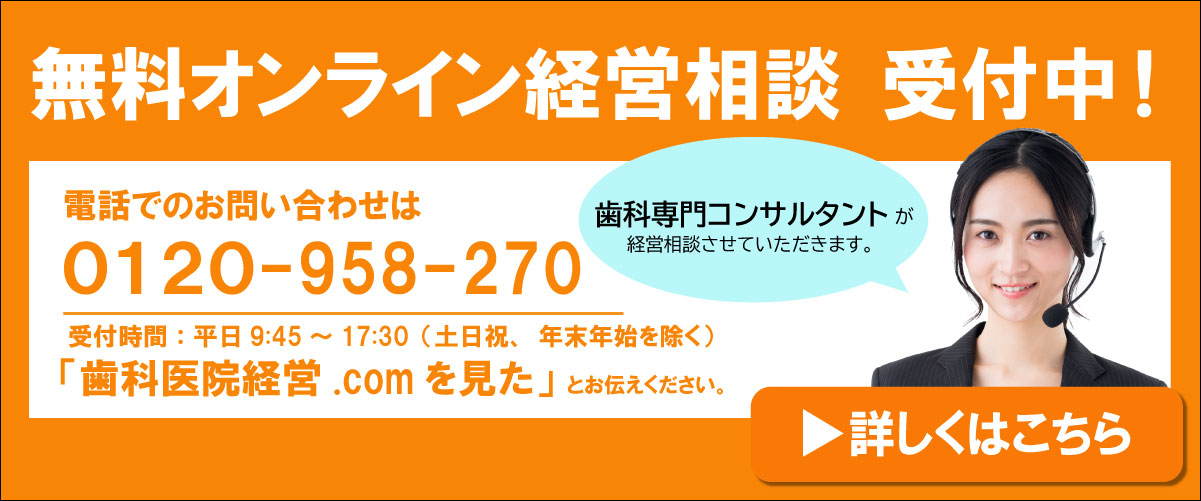【歯科診療報酬改定速報vol.8_専門機能強化】「なぜ、あなたは当院を選ばなければいけないか」唯一無二の連携で地域を救う
- コラムテーマ:
- 未分類
いつもお世話になっております。
株式会社船井総合研究所、歯科支援部リーダーの
山本 喜久でございます。
お忙しいところ、こちらのコラムをご開封いただき、
誠にありがとうございます。
■中央社会保険医療協議会(中医協)令和7年9月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001560014.pdf
こちらの概要は、来年度の2026年(令和8年)歯科診療報酬改定における指針となるため、
下記内容を先立って把握~対応の検討を進めていくことで、
時流(時代の流れ)に沿った歯科診療の提供を叶えることができます。
そもそも、なぜ「時流(時代の流れ)に沿った歯科診療が必要か?」ですが、
国民皆保険制度上、“国として、進めたい方向に点数を付けていくこと”が明らかです。
前回改定では「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」から「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと変わり、高齢者のオーラルフレイル対策や小児の口腔機能発達不全症など、予防管理領域が強力に推進されました。
これは、「訪問診療にならない人を増やす」という一次予防的な社会課題の解決に点数を付けた結果です。
もちろんながら、「点数が高いから、時流適応しましょう」というものではありません。
国が推進する方向を知ることは、「日本の社会課題を医療行為を通じて解決していくこと」であり、その結果、点数がついてくるというものです。
2026改定の鍵「専門性機能を持つ歯科診療所」
今回の改定議論の方向性において、以前のテーマに加え、特に注目すべきは
「目指す歯科医療提供体制の方向性」の中で明確に示された、
歯科医療機関の機能分化です。
中医協資料からは、かかりつけの歯科診療所に加え、
「専門性機能を持つ歯科診療所」
の役割と機能の確保が求められていることが読み取れます。
これはつまり、かねてより言われている「骨太の方針」のうち、
①糖尿病と歯周病の関わり(医科歯科連携)
②オーラルフレイル対策(口腔機能管理)
③多様化するニーズと地域特性を踏まえた、高度な専門的歯科医療の提供
の③が今後の大きなポイントであり、この「高度な専門性」の具体的な対象として、障碍者歯科、摂食嚥下リハビリテーション、そして全身疾患を持つ有病者への対応が挙げられます。
「専門機能」の核となる3大テーマの推進
1. 地域完結型体制への障碍者歯科医療の確立
(日本障害者歯科学会(JSDH)様の視点から)
高齢化と医療の進歩により、心身に障害を持つ方や、医療的ケアが必要な方の歯科ニーズは増大し続けています。日本障害者歯科学会が提唱するように、大学病院などの専門施設に集中している現状から脱却し、地域全体で受け入れ、継続的な口腔管理を提供できる体制の構築が急務です。
推進されるポイントは、「専門性を持った上での地域連携」です。
①専門機能への評価強化
行動調整、鎮静法、全身管理など、専門性の高いケアを提供するための設備・知識を持つ医院に対する加算・評価が明確化される見込みです。
②連携パスの明確化と義務化
地域病院・福祉施設・かかりつけ歯科診療所との間での多職種連携を通じた、シームレスな情報共有と治療連携が、診療報酬の算定要件に組み込まれる可能性が高まります。これは、特定の専門分野における「たらい回し」を解消し、地域で完結する仕組みを構築するためです。
2. QOLと生命予後を支える摂食嚥下機能の管理
(日本摂食嚥下リハビリテーション学会様(JSDR)の視点から)
オーラルフレイル対策の中心である「口腔機能管理」の中でも、「食べる・飲む」機能、すなわち摂食嚥下機能の維持・回復は、患者様のQOLと直接的な生命予後に最も深く関わります。日本摂食嚥下リハビリテーション学会様が示す通り、単なる機能維持ではなく、積極的なリハビリテーションが求められています。
①積極的なリハビリテーションへの評価
従来の機能評価に加え、言語聴覚士(ST)や管理栄養士(RD)といった多職種と連携し、専門的な訓練や指導を行う摂食嚥下リハビリテーションに対し、より高い評価がなされる期待が高まります。
②治療の「結果」への評価
有床義歯や補綴装置の提供後、「噛める装置を付けた先に、口腔機能がどう変化したか」だけでなく、「何を、どれだけ食べられるようになり、栄養状態にどう貢献したか」という治療の先の結果に対し評価する体制の推進が始まります。これにより、歯科医院における管理栄養士の活躍が、診療報酬を通じて強く後押しされると期待できます。
3. 全身疾患を持つ有病者への安全な対応
(日本有病者歯科医療学会(JJMCP)様の視点から)
高齢化に伴い、歯科に来院される患者様の多くが、高血圧、糖尿病、心疾患など複数の全身疾患を抱え、多剤を服用しています。日本有病者歯科医療学会が重要視するように、安全に歯科治療を提供するための医科歯科連携と治療リスク管理の体制強化が必須となります。
推進されるポイントは、「全身状態を踏まえた周術期管理」です。
①リスク評価と情報共有の加算
治療前に詳細な問診と服用薬剤リストを確認し、出血傾向や感染リスクを評価する業務に対し、新たな評価がつく可能性があります。特に、**服用薬剤が多い患者様に対するリスク管理は、今後より重視されるでしょう。
②かかりつけ医等への情報提供の拡充
周術期(抜歯や外科処置など)において、内科や主治医に対し、治療計画とリスクを共有し、必要な指示(休薬など)を得るための情報提供料が拡充されることが予想されます。
今回の診療報酬改定は、予防管理(一次予防)の次に来る、専門機能の確保と機能分化を強く促すものと読み取れます。特に、高齢化社会において避けて通れない障碍者・有病者への対応と、摂食嚥下リハビリテーションの3つは、今後、地域医療の質を担保するための必須機能となるでしょう。
貴院の診療方針を決めるうえで、
この「専門性機能の強化」という時流は、
単なる加算点数の話ではありません。
「貴院が地域でどのような存在意義を持つべきか」という問いかけです。
目の前の患者様のニーズを深く捉え、
情熱とビジョン(羅針盤)を明確にし、
能力とリソース(船の性能)を磨くことで、
「国が進める地域完結型医療の受け皿」
としての地位を確立する、大きなチャンスとなります。
この機会を活かし、地域社会における貴院の「不可欠な存在」としての進化を目指しましょう。
今回の時流を読み取り発信していくことで、
ますますの業界発展ならびに、
ご来院いただく患者様の“健口=健康”を延伸し、
より強い日本の創造に寄与できればと存じます。

コラムを最後までお読みいただきありがとうございました。
来たる令和8年度の診療報酬改定の情報公開に備え、今後は診療報酬改定に関する情報 や、現場で役立つコラムを船井総研公式LINEアカウントにて【先行配信】いたします。
令和8年の診療報酬改定に向けた情報を今後もできるだけ早くお伝えをさせていただきますので、是非この機会にご登録ください。
◾️この記事を書いたコンサルタント

山本 喜久
関西学院大学法学部出身。新卒で船井総合研究所に入社。
大学時代から、難関校専門の塾講師として活躍。その時の経験から「人に教える」ことを最も得意とし、それを応用したカウンセリング体制の構築には定評がある。経営者に寄り添いながら、粘り強く「歯科医院経営者の夢を叶える」ことをコンサルタントとしての信条としている。
LINEはじめました!
LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!
無料経営相談受付中!
メールマガジンのご案内
歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~
歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。