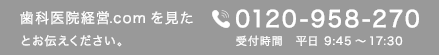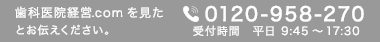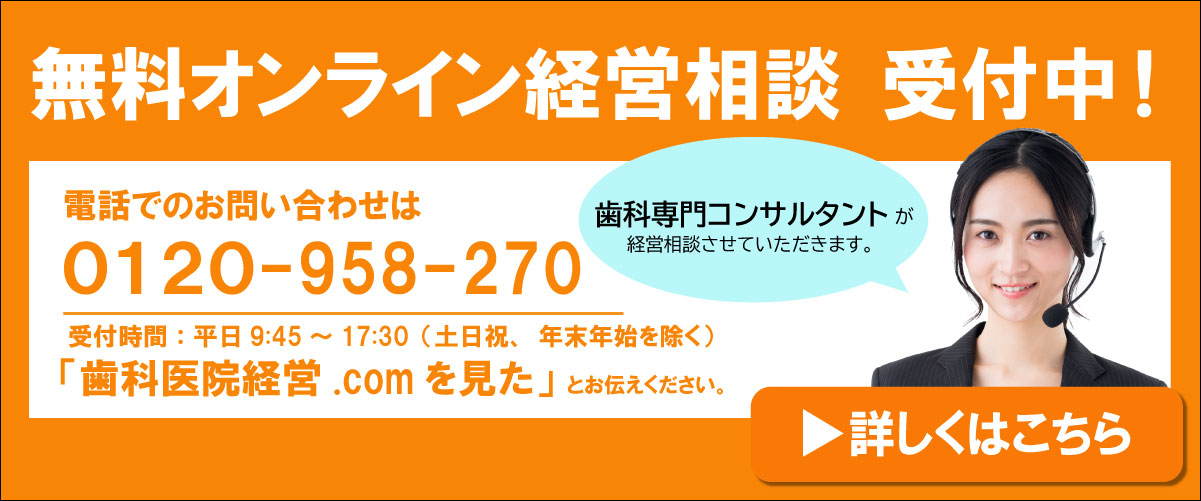【いよいよ待ったなし!】ついに始まる「医科歯科連携シナリオ」
- コラムテーマ:
- 未分類
皆様
いつも本当にお世話になっております。
株式会社船井総合研究所 歯科支援部リーダーの
山本 喜久でございます。
本日もお忙しい中、このコラムを開いてくださり心から感謝いたします。
今回お伝えするテーマは、2026年の診療報酬改定を見据えた「歯科業界の未来を大きく変える転換点」です。これは間違いなく、今後の医院経営を左右する最重要テーマのひとつ。ぜひ最後まで目を通していただき、医院の未来戦略に役立てていただければと思います。
中医協からの最新情報を緊急キャッチ!
先日、中医協から新たに公開された資料。これはただの追加資料ではありません。
「来年度改定の方向性を明確に示す“羅針盤”」と言っても過言ではない内容です。
■中央社会保険医療協議会(中医協)令和7年9月10日開催
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001560014.pdf
この情報をどれだけ早く掴み、どう医院経営に活かしていくか。ここで行動に移せるかどうかが、競争力を大きく左右します。情報を知ること自体には価値はありません。大事なのは「どう動くか」です。行動した医院が、地域で選ばれ、次の時代に生き残っていきます。
今こそ「時流」と「医科歯科連携」に向き合う時
診療報酬は、国が「進めたい方向性」に点数をつけていきます。
だからこそ、点数をただ追いかけるのではなく、国の方針を読み取り、社会課題解決に取り組む医院こそが結果として高く評価されます。
医院の方向性を決めるときに必要なのは、
will(やりたいこと)
can(できること)
must(求められること)
の3つの視点です。特にmustを正しく理解し、行動に移すこと。これは医院の生存戦略そのものであり、地域医療への責任でもあります。
糖尿病と歯周病「エビデンスに基づく必然の連携」
今回の改定で最も重視されているテーマが、この「糖尿病と歯周病の連携」です。
なぜここまで強調されるのか?それは、確かなエビデンスに支えられているからです。
・歯周病治療を行うとHbA1cが0.4〜0.6%改善する
・歯周病の炎症コントロールは糖尿病の重症化予防に直結する
・糖尿病患者は健常者に比べて歯周病罹患リスクが2〜3倍高い
つまり、歯科と医科が手を取り合うことで、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費を削減し、国民の健康寿命を延ばすことができる。この大義があるからこそ、国はこのテーマを骨太の方針に据え続けているのです。
改定で想定される具体的な歯科医院の役割
ここからは「国が求める方向性」を、医院でどう形にするか。資料から見えるのは、従来の「情報提供」にとどまらず、歯科が医科との連携をリードしていく姿勢です。
1. 内科との「連携パス」の強化
これまでは紹介状や情報提供書のやり取りが中心でした。しかし、今後はそれだけでは不十分です。
・HbA1cの値や服薬状況
・歯周治療の進行度合い(ポケットデプスや出血指数)
といった情報を、双方向かつ継続的にやり取りする体制が評価の対象になると考えられます。ここで重要なのは「形式的な報告」ではなく、「患者の全身管理を一緒に担っている」という姿勢です。
2. 院内スクリーニングの導入
血糖値やHbA1cを歯科医院で測定できる体制を整えることも、評価対象に含まれる可能性があります。定期メンテナンスや初診時に簡易的なチェックを導入すれば、歯科が糖尿病発見の入口になる。これは社会的にも極めて大きな意義があります。
測定機器やデータ管理フローを早めに準備しておけば、改定と同時に動き出すことができます。
3. 患者教育と動機付けの強化
患者さんに「歯周病治療が血糖値改善につながる」と具体的に伝えることは非常に効果的です。さらに栄養士・管理栄養士と連携した食事指導や禁煙支援、生活習慣改善プログラムを展開すれば、患者の自己管理意欲は確実に高まります。
今後はこうしたアウトカム(成果)が診療報酬に反映される流れになる可能性が高いです。
医科歯科連携は経営面での大きな可能性もある
臨床的な意義にとどまらず、このテーマは医院経営にとっても極めて大きなチャンスです。
①新たな患者層を取り込むチャンス
日本には糖尿病患者が1000万人以上いると言われています。この層に向けて「歯周病治療で全身の健康を支える」というメッセージを発信すれば、新しい集患ルートが広がります。
②医科との信頼関係が深まる
内科医や糖尿病専門医と協力し合うことで、自然と紹介や逆紹介の流れが生まれ、地域の医療連携における立ち位置が強固になります。
③医院ブランドの差別化
「口だけでなく体全体を診る歯科医院」——この打ち出し方は、地域で圧倒的な存在感を発揮し、選ばれる理由となります。
今、取り組むべき準備とは?
・医科との連携フォーマットや共有シートの整備
・HbA1cなどの測定機器導入とフローの検討
・教育ツール(パンフレット・動画・説明資料)の作成
・スタッフ研修(糖尿病の基礎知識や連携フロー)
これらを今から準備しておけば、改定スタート時に「すぐに動ける医院」になれます。スピード感こそが差を生むのです。
《まとめ》
糖尿病と歯周病の連携は、もはや“加点のオプション”ではありません。
地域で生き残り、選ばれるために絶対に取り組むべき戦略です。
2026年改定を、ただの制度変更として受け身で迎えるのか。
それとも医院の未来を切り拓くチャンスとして活かすのか。
その分かれ道は、まさに「今この瞬間」にあります。
次回はさらに、点数化の方向性や施設基準について具体的に解説し、医院で即実践できる形まで落とし込んでいきます。
ぜひ、このコラムを引き続きチェックしてください。
一緒に、歯科の未来を創り上げていきましょう。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
◾️この記事を書いたコンサルタント

山本 喜久
関西学院大学法学部出身。新卒で船井総合研究所に入社。
大学時代から、難関校専門の塾講師として活躍。その時の経験から「人に教える」ことを最も得意とし、それを応用したカウンセリング体制の構築には定評がある。経営者に寄り添いながら、粘り強く「歯科医院経営者の夢を叶える」ことをコンサルタントとしての信条としている。
LINEはじめました!
LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!
無料経営相談受付中!
メールマガジンのご案内
歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~
歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。