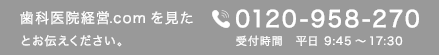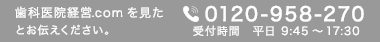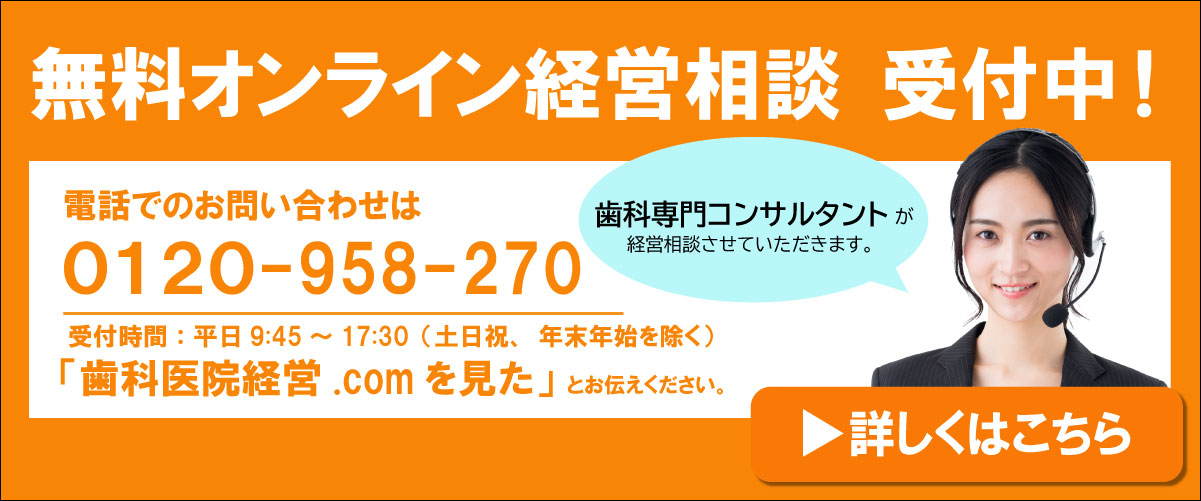【歯科診療報酬改定速報vol.5_機能評価】中医協資料から読み解く大転換と実務対応
- コラムテーマ:
- 未分類
皆様
いつも大変お世話になっております。
株式会社船井総合研究所 歯科支援部リーダーの山本喜久でございます。
このたびは、本コラムをご覧いただき、心より御礼申し上げます。
さて、本日のコラムも、来年に控えた保険改定に関する内容をお届けします。
9月中旬に、中央社会保険医療協議会(中医協)が公表した最新資料は、既にご確認いただけたでしょうか。
この資料は、2026年改定の方向性を示す「次期標準」であり、今後の医院運営の指針となるものです。
この情報をいち早く掴み、対応に着手する医院と、静観する医院とでは、来年以降の経営体制に明確な差が生じると予測されます。私たちは公開直後から分析を行い、その重要ポイントを緊急でお届けします。
2026年改定に向けた「実務指針」の確認
■中央社会保険医療協議会(中医協)令和7年9月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001560014.pdf
この資料は、2026年歯科診療報酬改定の実務指針となる見込みです。
現時点でこの要点を把握し、院内の対応検討を開始することで、時流に合致した診療体制へと確実に移行する準備を整えることができます。
国民皆保険制度の下では、国が推進したい医療や体制に対して、診療報酬が重点的に配分されます。
今回の方向性は、これまでも繰り返し示されてきた「骨太の方針」—医療を通じて社会課題の解決を目指す—に深く結びついています。
本稿では、中でも特に重要度の高い「歯科技工士の活躍強化」と「有床義歯の評価見直し」に焦点を絞り、資料から読み解くべきポイントを整理します。
医院の診療方針は、
will(院長が目指す診療)
can(医院が得意とする診療)
must(国や社会から求められる診療)
の三軸のバランスによって決定されます。
時流を正確に捉えることは、この三軸を現実的な視点でアップデートするための最短ルートです。
国の方針と協調し、業界全体で社会課題解決に貢献できる体制づくりを進めてまいりましょう。
【役割強化】義歯評価は「完成」から「機能改善」へのシフト
今回の主要な柱の一つであるオーラルフレイル対策の推進は、義歯診療に携わるすべての医院に直結するテーマです。
資料からは、有床義歯の評価項目に関する示唆が始まっており、評価の重心が「装置の完成」から、「装着後の機能改善(咀嚼機能や発話機能の向上)」へと移る方向性が強く示されています。
この構造変化が意味するもの
これは、技工士の設計・精度 → 治療アウトカム(患者の治療後改善結果) → 評価という直結構造が、今後より明確化する可能性が高いことを示唆しています。
義歯が患者さんの「食べる・話す」機能の向上に確実に寄与することが、国の目標とする健康寿命の延伸に貢献することは明白です。したがって、機能改善という結果を促す点数体系への移行が想定されます。
今から取り組むべき実務対応(今日から動ける3ステップ)
そこで、この構造変化を経営の機会とするために、すぐに着手すべき具体的なアクションを3つご提案します。
1. 「機能」を起点とした発注フローへの大転換
評価の軸が「機能改善」にシフトする以上、指示書と発注時のコミュニケーションも「色や形」から「機能の定量目標」に切り替える必要があります。
発注時に共有する情報の刷新:
現在の口腔機能の評価(例)としては、以下の内容が考えられます。
患者さんの現在の食形態(例:軟飯、きざみ食)、簡易咀嚼テストの指標、嚥下障害の有無、そして自覚的な不便さを明確に伝える。
達成目標の設定:
義歯装着後に目指すべき具体的な目標値(例:食形態のレベルアップ、咀嚼能率の〇%改善、発話明瞭度の改善度合い)を、技工士と共有する。
指示書の記載事項の変更:
診断(現状)→ 設計(意図)→ 製作(技法)→ 装着後評価(結果)まで、一連の流れの中で同じ機能KPIを追跡できる欄を新たに設ける。
目的:単なる製作依頼ではなく、「機能改善」を前提とした設計へと意識を集中させ、義歯の役割を「モノ」から「治療結果を生むツール」へと転換する。
2. 装着後の機能レビューを院内の必須プロセスへ組み込む
「機能が改善したか」が評価軸になるため、装着後の客観的な機能評価と、その結果をチームにフィードバックする仕組みが不可欠になります。
完成検査項目の追加:
従来の適合や咬合のチェックに加え、「装着後の機能変化」の定量的・定性的な評価項目を必ず実施する。
評価例:簡単な咀嚼テスト(ガムやグミ)、発話明瞭度テスト、QOL(Quality of Life)に関する患者主観指標(アンケート)の聴取。
フィードバック方法の構築:
定量指標(客観データ)と患者さんの生の声(定性データ)という両輪の情報を整理し、技工士へ必ずフィードバックするルールを確立する。
月次PDCAサイクルの運用:
義歯の不適合・再調整率、目標達成率(機能KPIの達成度)などのデータを院内で可視化する。このデータをもとに、歯科医師・歯科衛生士・技工士が参加する会議を定期的に開き、継続的な改善サイクルを回す。
3. 技工士が“顔の見える専門職”として歯科医院での役割を変化する
義歯の機能改善において技工士の役割が拡大するため、患者さんに対する技工士の専門性の可視化と、院内チーム内での情報共有・連携を強化する必要があります。
デジタルプレゼンテーションの標準化:
IOS、CT、FaceScanなどのデジタルツールを用いた症例データを利用し、患者さんに対して完成物のイメージだけでなく、設計の意図と機能改善のプランをプレゼンテーションする。
必要症例における同席説明:
特に難症例や複雑なケースでは、技工士が診察室に同席し、義歯設計の専門的な意図を直接説明する。これにより、患者さんの納得度(インフォームド・コンセント)を深め、治療への主体的な参加を促す。
競争軸を「データ活用力」に転換:
単に「設備量が多い」ことを強みとするのではなく、診断データ→設計データ→説明→評価という「データ統合活用力」を医院の競争力の源泉とする。
役割分担の文書化:
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の役割に加え、AI自動デザインなどのデジタルの役割まで明確に文書化し、人 × デジタル × AIの理想的な連携体制を院内で確立する。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
今回の方向性は、歯科医師・歯科衛生士・技工士の三位一体チームが連携し、患者さんの機能改善=健康寿命の延伸という「結果」をもって応えることを求めています。
本稿では、この流れを加速させるための具体的な実務対応の要点を共有いたしました。
この改定を進化の契機と捉え、業界全体の質を高め、来院される患者さんの「健口(けんこう)」を着実に伸ばし、日本の活力向上に貢献していきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
LINEはじめました!
LINE友だち登録で、歯科経営専門コンサルタントのコラムを読むことができます!
無料経営相談受付中!
メールマガジンのご案内
歯科医院経営コンサルティングレポート~船井流1000院からの成功事例報告~
歯科医院コンサルティング実績10年! 現場で積み上げた歯科経営成功事例満載のメールマガジンです。自費UP、増患、ホームページ対策、スタッフ育成、組織づくりなど、読んだ院長だけが得をする「3分でわかるノウハウ」を大公開します。